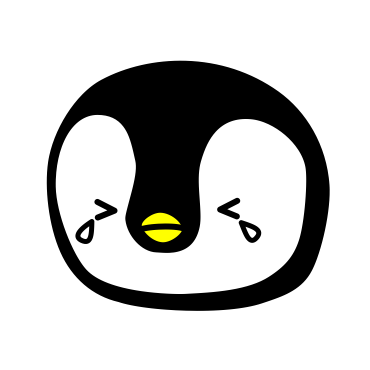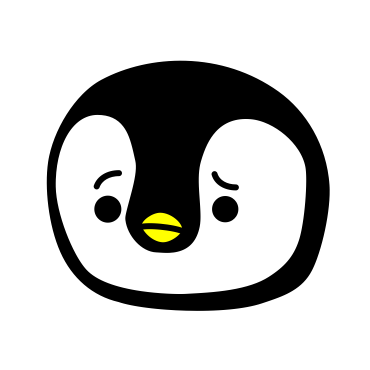今回は、「引き寄せの法則」とか成功哲学の元ネタになっているニューソートについての本のレビューです。
「引き寄せの法則」は、ニューソートと呼ばれる思想の流れを汲んでいると言われています。
そのためここでは、ニューソートの系譜と意義について記された本書について、取り上げました。
読み進むうちに、「引き寄せの法則」と非常に近い内容を含んでいることが分かってきます。
本書では、ニューソート思想を展開した様々な人物の紹介がなされており、彼らの思想について、ほとんど同じ内容の説明が繰り返されています。
そのため前段として、ニューソート思想がどういうものなのかについて、簡単に記しておきたいと思います。
ニューソートの大まかな特徴は、以下のとおりです。
- キリスト教プロテスタントのカルヴァン主義への反発から生まれた思想。
- 神を人格的なものでなく、あまねく存在し宇宙を構成している物質と捉える。
- 宇宙全体を一つの神とし、その中にある人間にも神的なものを認める。
- 愛を神の意志が地上において表現されたものと捉え、病気や死をその欠如と見る。
- イエスによる人々への癒やしを、遍在する物質としての神の力によるものと考える。
- イエスが使った力は万人にも宿り、かつ利用可能なものと見なす。
- 「原罪」などは存在せず、繁栄を神の意志と捉える。
もくじ
「第一章 ミカエル・セルヴェトゥス・ヴィラノヴァヌス」について
ニューソートの発端として、スペインの学者・神学者のミカエル・セルヴェトゥス(ミシェル・セルヴェ)が紹介されている章です。
セルヴェトゥスの思想として紹介されている内容は、いわゆる一元論と呼ばれるものです。
そしてそれは、ワトルズ版の「引き寄せの法則」にかかれている宇宙一元論と、大枠において同じものと考えてよいでしょう。
つまり、すべてのものがただ一つのものから生まれたと捉え、人間もその一部と見なすというような考え方です。
これは「人間の中にも神聖なものがある」という考え方ですから、神への冒涜であると解釈される部分があったものと思われます。
実際、セルヴェトスは、ジョン・カルヴァンが統治するジュネーブで、火あぶりの刑に処されています。
こわいよぉ。
宗教を古い考えから開放したイメージだけど、実際には、自分らが正しいと思うのと違うことを主張するヤツは、殺してまで排除したってコトなんだろうネ。
「第二章 源流・スウェデンボルグ」について
ニューソートに多大な影響を与えているのが、スウェーデン王国出身の科学者・神学者・神秘主義思想家である、このエマニュエル・スウェデンボルグです。
思想的な特徴としては、繁栄を目指し広がりゆくエネルギーのようなものを唯一の「神」として捉えている点が挙げられます。
そこから、人間には生産的であることが求められ、富や物質的幸福は肯定されるべきものと考えられています。
これは、人間が生来持ち合わせている「繁栄を目指す」という傾向を肯定するものです。
その意味では、「人間には原罪がある」として、否定を出発点としているとも言える旧来のキリスト教的な考え方と、大きく違っているものと考えられます。
また、「あらゆるものの源流としての「神」が生命に流れ込む現象である「神的流入」が悪を取り除く」と主張されていますが、これは「引き寄せの法則」における「引き寄せ」に通じる考えと言えるでしょう。
ただし、「神的流入」のためには、スウェデンボルグが考えるところの「宗教的に正しい生活」を送ることが重要だとされており、「引き寄せの法則」で「望むものをイメージせよ」とされている点とは、まったく違っています。
なお、スウェデンボルグによれば病気は低次の心(イド)によるものとされ、この「イド」というのは、「エス」とも呼ばれるもので、後にフロイトが定義し利用した精神分析上の概念です。
意味合いとしては無意識に相当する部分のことであり、感情、欲求、衝動等が詰まっているところとされています。
フロイトは心をエゴ、スーパーエゴ、イド(エス)の三つの様態から捉えましたが、その基礎となる考え方はスウェデンボルグが夢の象徴の意味を吟味し叙述したことから始まるとされているとのことです。
当サイトでは「引き寄せの法則」を無意識の働きによるものと考えますが、「引き寄せの法則」の源流であるニューソートの、しかもその源流と言えるスウェデンボルグの考えの中に、すでに無意識についての議論の始まりが見て取れるのは、非常に興味深いところです。
「第三章 フィニアス・パークハースト・クィンビー」について
前段として、クィンビーに大きな影響を与えたメスメルについての説明がなされています。
ウィーンの医師であるフランツ・アントン・メスメルは、「宇宙的流体」の理論を展開しました。
「宇宙的流体」とは宇宙のあらゆる生命体に影響を及ぼすものであり、これを自分の体から患者に注ぎ込むことで健康が回復できるとメスメルは考えました。
また彼は、この「宇宙的流体」を伝導させる力を「動物磁気」と呼んでいます。
なお動物磁気説は、後に行われたベンジャミン・フランクリンらの調査によって、「想像力によるもの」として否定されています。
実際、メスメルは治療にあたって、患者を催眠状態にしていたとのことです。
フィニアス・パークハースト・クィンビーは、自らの結核の克服体験から、病気は誤った信念の中にしか存在しないと確信し、メスメル派の治療家となってニューソートの枠組みをつくり出すきっかけを得ました。
当サイトは「引き寄せの法則」研究所ですから、クィンビーの思想の中で、「引き寄せの法則」に深い関係のある点を見てみます。
ポイントとなるのは、「信じることが結果をもたらす」という点です。
これはまさに、「引き寄せの法則」の萌芽と言うべきような考えです。
クィンビーは、宗教による誤った想念が結果として病気を作ると考えていました。
ここでは、そのような考えがどうして生じたのかを確認しておきましょう。
クィンビーは、数々の患者に治療を加えました。
その際、なぜ病気が生じるのかということを考察したわけです。
そこには、聖職者が宗教的な解釈により「これが罪だ」とするような行為というものがありました。
つまり少なからぬ人が、自分の行動について「罪を犯してしまった」と捉えて悩み、そのことが原因で神経症などを起こしていたということです。
このような状況は、その昔、イエスが周囲の人々を癒やしていた状況と類似しています。
当時もまた、律法学者がユダヤ教の解釈を示し、それに従わない、合わない人間が虐げられるということが行われていたのです。
歩けない者、目の見えない者、耳の聞こえない者は、罪深いがためにそうなったのだと排斥されていました。
そんな彼らを癒やしていったのが、イエスです。
クィンビーは、自らをイエスに重ねて治療を行い、不当な解釈により病気や苦しみを生み出す宗教にこそ問題があると考えました。
このように従前の教会組織に対する強い反発の精神は、ニューソート全般を貫く一つの特徴と言えます。
なお、彼もまたスウェデンボルグと同様に、人の心は相互に直接的に作用しあったり影響を及ぼし合っているとし、無意識的な反応の力について考えていたようです。
「それぞれの人間の中にも神の性質は宿っているので、おかしな考えを追い出せば病気は治る」と、そんな感じに考えていたようですネ。
「第四章 ウォレン・フェルト・エヴァンズ」について
スウェデンボルグ主義者であるエヴァンズについての紹介が書かれた章です。
しかし、その説明は従前のものと似通っており、エヴァンズの思想がスウェデンボルグと何が違うのかについては、本書だけはあまり明確にはならないように思います。
クィンビーと明確に異なるのは、いわゆる催眠術的な手法を捨てたというところでしょうか。
いずれにせよクィンビーもエヴァンズも、イエスによる癒やしを「科学」と捉えているようです。
しかし、霊的なものについて科学と言われると、やはり違和感があります。
もしかすると科学技術が発展する時代状況の中で、その究極の形として、無病・不死を実現する技が夢想され、それがイエスの為した癒やしの正体であると考えたのかもしれません。
エヴァンズは神的流入による治療といったものを実証可能と捉え、これを「クリスチャン・サイエンス」と呼んでいたとされています。
科学と考えると、同じ状況で誰が操作しても同じ結果が得られることが必要ということになるでしょう。
おそらく、自らの治療によって現に症状が改善する人が多数存在することをもって、実証されたものと見ていたとも考えられます。
これはいまさらの指摘ではありますが、エヴァンズは現在では心療内科や精神科で行われている治療を、キリスト教的な信仰をベースにして行っていたと見ることができるでしょう。
そう言われると、かなり違和感があるなぁ。
「第五章 クリスチャン・サイエンス」について
クリスチャン・サイエンス教会を作ったメアリー・ベーカー・エディーについての章です。
彼女は、最盛期には1600もの教会を運営し、26万人以上の会員を集めたとのことです。
しかし少なくとも本書の内容からは、スウェデンボルグ以降のクィンビーやエヴァンズらの思想と大きく変わるところはないように思えます。
非常に大きな組織を作ったところが、違う点でしょうか。
ニューソート運動が、教会組織への批判から生まれたものとも言えるにも拘らず、また大きな組織を作り上げるところに回帰しているところは、注目すべき点かもしれません。
しょうがねぇなぁ。
ただ、ニューソートのもともとの考えとゼンゼン違う感じはするよネ。
「第六章 偉大なる大衆思想家」について
ニューソートの影響を受けている思想家が多数紹介されている章です。
もっとも有名なのは、名著『自己信頼』で知られるラルフ・ウォルドー・エマソンでしょうか。
『ねじの回転』で知られるヘンリー・ジェイムズの父でスウェデンボルグ主義の宗教哲学者であるヘンリー・ジェームズ・Sr.なども紹介されています。
主張されている内容としては、輪廻の思想を取り入れたりなど多少のバリエーションはあるものの、セルヴェトゥスやスウェデンボルグが展開した考えと、大枠においては同じと言って良いでしょう。
また、初期のニューソートで見られたようなキリスト教の新たな捉え方の模索や教会組織への批判などの純粋さのようなものがある程度薄まり、現世利益的な色合いが増してきたようにも思われます。
そうした流れもあってか、本章で指南されている実践の方法は、「引き寄せの法則」や「成功哲学」に非常に近いことが分かります。
具体的には、以下のような内容になっています。
- 成功をイメージする。
- それがすでに起こったように考える。
- イメージしたものと同調することで現実化できる。
ニューソートでは願望実現の根拠として、遍在する創造主としての「神」を考えているところが違うだけという印象さえあります。
逆に言うと、ニューソートから神の概念を抜き去ったり、その影を薄くしたりすると、「引き寄せの法則」や「成功哲学」になるということです。
実際のところ、ワトルズ版の「引き寄せの法則」では、ニューソートにおける「神」が、「形のない物質」「思考する物質」「知性のある物質」と表現されています。
ニューソートでは、その根本に信仰があるためか、病いや老いをただの思い込みや迷信とまで主張している場合が少なくないようです。
現世利益を否定するなどして現実の価値を転倒させるのが宗教の役割だとも言えますが、いささかやりすぎのようにも思われます。
通常考えられている死は、本当は死ではないというようなことも言われているようですから、病いもじつは病いでないのだというような物言いがなされているのかもしれません。
ニューソートの特徴としては、他にも、正しくあるということが前提とされている点が挙げられるでしょう。
「神」と呼ぶものの助けによって進むという話なのですから、そうなるのも当然かもしれませんが、意図や行動が「善」であるときにのみ、正しく力が発揮されるとされている訳です。
一方で「引き寄せの法則」の考え方を言えば、理想的な状態をありありとイメージし、実現したときの感情を味わっていれば現実化する、ということになります。
つまり、宇宙の法は自動機械のようなものであって、善悪のような倫理的判断が間に挟まる余地はない、とさえ解釈できるわけです。
そうは言っても、しばしば「引き寄せの法則」や「成功哲学」では、「善きことを行え」というような倫理性が登場します。
その点もまた、ニューソートの影響によるものだろうと考えられます。
実際、アトキンソン版の「引き寄せの法則」がにおいては、「高い実現」「低い願望」といった固定された価値判断を強く思わせるような書きぶりが見受けられます。
時代を経るにつれて、だんだんと「引き寄せの法則」っぽくなってきたね。
昔は、宗教が絶対的に従わないとならないモノで、そこに切実な争いだとか議論があったんだけど、だんだんとそこまでのチカラを持つモノじゃなくなったってコトでしょう。
解題
本書には第七章以降もあり、ニューソートの大きな団体についての解説などがなされています。
その中には、成功哲学を説いたとして有名なジョセフ・マーフィーやマクスウェル・マルツ、「生長の家」を創設した日本の谷口雅春の名前も出てきています。
しかし、大枠の思想的な内容としては同じことの繰り返しになっていますので、省略をしました。
さてニューソートですが、すでに書いたとおり「引き寄せの法則」や「成功哲学」の元になっていることは明らかだろうと思います。
その概要を知れば、ロンダ・バーン版の「引き寄せの法則」で量子力学の話題に絡めて語られている点も、納得がいくかもしれません。
つまり、超ひも理論での「すべてが一つの物質からできている」という考えが、ニューソート的な「神」に関わる一元論と似通った部分があり、親和性が高いということです。
「引き寄せの法則」との関連だけでなく、ニューソート自体についても、少し考察を加えておきます。
まずもって、ニューソートの眼目はと言えば、イエスの思想の再評価ということになるのではないでしょうか。
本書では、ニューソートは三位一体説への批判から始まったとされていますが、重要なのは、イエスの存在と行為をどう捉えるかにあると思われます。
そもそもキリスト教は、イエスの死後三百年以上経ってから作られ、「イエスはすべての人間の罪を贖うために十字架にかけられた」という、いわゆる「贖罪論」を通してパウロが広めたものと考えられます。
しかし、それを広めるための土台としての教会組織については、色々と問題があるようです。
例えば本書においても、三位一体説を批判したセルヴェトゥスが、カルヴァンによって火あぶりの刑にされたとの記述があります。
時代状況もありますし、異端の人間を悪魔と見なして行ったということかもしれませんが、自らの考えに合わないものを排除しようとする心の傾向は、イエスの教えとは真逆のものであると言わざるを得ません。
また現在においても、一般的に教会組織においてなされる原罪意識や悔い改めの必要性についての強調に関しては、恐怖によって人々を支配するための手法とも取られかねないほどのものです。
このような脅しが信者の心が病んでしまう原因となっている状況は、ニューソートが生まれて百年以上経ったいまでも変わらずに存在すると言えます。
イエスが律法学者などを批判していたのと同じ状況が、イエスを救世主と捉えるキリスト教の組織から生み出されているのは、まったく皮肉なものと言わざるを得ません。
原罪という観念によってなされる聖職者による「恫喝」とはまったく逆に、社会から虐げられた人々に愛をもって接し、病いを癒して、それぞれの存在を認めたのがイエスです。
こうした態度によって、他人を排除などしなくても「必要なすべては自ずと与えられる」ということを示したのが、イエスの教えにおけるキリスト性の核心だと言えるでしょう。
その点から言えば、三位一体説に拘泥し、自らの保身と繁栄、そして他者への排斥に身をやつす従来の教会組織へのニューソート的な批判は、当然のものと考えられます。
また他の論点として、ニューソートの考え方には、あらゆる生き物に必要である「いかにして形作られ、成長をしていくのか」という情報が「神」という外側から与えられるものだと捉える発想があるように思われます。
現在では、DNAによって伝えられると判明していることですが、何十億年もの時間を掛けて作られた生命の不可思議に厳粛さを感じ取り、超自然的な存在による支配を想定するのは、おかしなことではないでしょう。
同時に、無意識の働きや儀式などによるプラセボ効果についても、「神」の意志だと捉えているところが伺えます。
つまり、旧来の教会組織への批判から生まれたイエスや「神」の捉え直しと、不可思議な生命の成り立ち、無意識的な働きなどについての説明の必要から生まれたのがニューソートであると考えることができるのではないでしょうか。
中でも、「神の一部として自分を信じるコト」「命や無意識が持つチカラの活用」ってあたりがポイントかなぁ。
全体的には、これまでの考え方に対する「コレじゃない感」「もっとイイのが欲しい感」があって、そこらへんがまさに、ニューソート(新たな思想)なんだろうネ。
【商品リンク】
⇒ amazon
⇒ 楽天
⇒ ヤフーショッピング